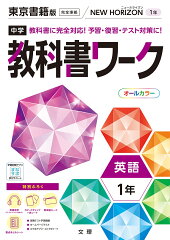最近、中高一貫校の中学生のお子さんを持つご家庭から以下のような悩みや相談をよく受けます。
・勉強しているけれども成績が上がらない。
・課題や提出物が未提出になっている。


中高一貫校の中学生の成績は内申点で評価されますが、この内申点の基礎となるのが、平常点(普段の学習態度、日々の小テストの点数など)と定期テストの点数です。
そこで、今回は主に中高一貫校に通っている中学生のお子さんの定期テスト対策と成績アップの勉強法ということで、平常点アップのための勉強法(プリント対策)と定期テストの点数アップのための勉強法について紹介します。
中高一貫校中学生~成績アップの勉強法
中学生成績アップ勉強法~プリント対策
中高一貫校はとにかく宿題や小テスト、プリントが多く、それらを整理するだけでも大変です。
特に入学したての中学1年生だとまずその多さに面食らうことでしょう。

この宿題や小テスト、プリントは平常点として加算されます。
これはやってくるのがあたりまえですので、やらない(提出しない)と平常点がものすごく下がります。
この宿題やプリントが未提出となっているという連絡がテスト前に学校からきて、「中学受験ではそこそこできたうちの子がなぜ?」と思われる親御さんは意外と多いです。
小学生の時はできたのにとか中学受験の塾ではできたのになぜ入ったとたんにできなくなってしまうのだろうと思うこともあるかもしれませんが、小学生の時とはプリントの量が違います。
また、中学受験の塾は、塾のカリキュラムが仮にプリントをなくしても別のプリントで何度も繰り返すうちに習得させるようなカリキュラムになっています。
それに加えて、塾の講師が意外とその場で細かく見て指導をしているので、言われたとおりにやればそれほど困ることはありません。
しかし、中高一貫校では一般的に中学受験の塾講師のように細かく学校の先生は見てくれず、本人に任せている(自主性を重んじている&そのくらいはできてあたりまえと考えている)ので、その点は気を付ける必要があります。
なので、まずは提出課題などについての情報をお子さんから出させる(ダメなら先生やママ友から情報を得る)ことが成績アップの最優先事項になります。
最初は親御さんがしっかりと面倒を見て、プリント整理ファイルを作るとか、置く場所を決めておくとかしてあげるとよいでしょう。
実際に私が家庭教師を担当している生徒さんについては、私はお母さんと協力して、そこまでの面倒も見ています。
ただ、正直何が出ているかはお子さんでないとわからないので、学校の出している情報(テスト範囲、小テスト、プリント、宿題など)についてお子さんから聞き出すことが一番苦労します。
テスト前になって、テスト範囲表を確認して「これ何?」とお子さんに聞いて、初めてその存在に気づくことも多いです(笑)。
まずは学校の情報を整理させるところからお子さんと共同作業ではじめましょう。学校でやっているプリントや小テストをこちらで把握できれば、あとはやってもらうだけです。
中高一貫校の生徒さんであれば、やるように言われたことはやるので、成績をアップさせることはそれほど難しくありません。
最低限科目ごとに分けて、ファイルに入れておいてもらうということだけでもやる習慣をつけるようにしてもらってください。
中学生成績アップ勉強法~定期テスト対策
プリントは提出するのが当たり前なので、実際には定期テストでどれだけ点数をとれるかが成績アップのための重要なポイントです。
とはいえ、中学受験を勝ち抜いたライバルが同級生なわけですから、生徒のレベルもそれなりに高いです。
なので、まずは平均点以上をとることを目指して定期テスト対策をすることが重要です。

中高一貫校の生徒さんはレベルが高いので、その中で平均点以上をとるためには、テスト前だけでなく毎日テストに向けて少しずつでもよいので勉強する必要があります。

実際に私の持っている中高一貫校の生徒さんは学校から通常の日は毎日3時間、テスト前はもっと勉強するのが当然というプリントを毎月配られています。
このように中高一貫校では毎日学習を継続することを前提としたカリキュラムが組まれていることが多く、テスト前だけ勉強しても量が多すぎて消化できないので、なかなか点数をとれません。
なので、普段から毎日勉強する習慣を身につけさせることが最初のスタートです。

中高一貫校の生徒さんの勉強スタイルとしては、①毎日勉強するのは英語と数学のみ、②国語と理科と社会はテスト前に集中して勉強する、③副教科は学校の授業をしっかりと受けて、(テストで点数がとれなくても)平常点でなんとかしてもらうか一夜漬けで対処というのが多い印象です。なお、ほとんどの個別指導塾もそのような方針で進めています。
具体的なテスト対策については、科目別に紹介します。
中学生定期テスト対策と勉強法~英語
英語は、学校の授業でやったところを中心に学校指定の教科書対応問題集等で教科書に出てくる文法、単語、長文の問題演習をして、テスト範囲の問題ができるようになれば、平均点はとることができます。
実際に、ほとんどの学校では、学校指定の教科書対応問題集はテスト後に提出課題として指定されていますので、提出課題がしっかりとできるようになればテストでも点数が取れるようになっています。
しかし、実際には提出課題について、1回だけ解いて提出するだけだとほとんど頭に残っておらず、テストの点数は悲惨な点数(赤点近い点数)となることが多いです。
そのため、学校指定の教科書対応問題集をヤフオクとかで購入するか(書店では売ってないことが多いので)、学校指定の教科書対応問題集とは別の教科書対応問題集(教科書ワークなど)で間違えた問題をできるようになるまで繰り返すことが大切です。
文法、長文、単語などの具体的な勉強法は下記で紹介していますので、必要に応じて参考にしていただければ幸いです。
なお、中高一貫校の中ではプログレス21という英語を英語で理解することを目的としたテキストを使っているところもあります。
そのような学校の定期テストについては別途対策が必要になります。
詳細は、下記を参照してください。
中学生定期テスト対策と勉強法~数学
数学は問題解いて解説読んでわかったで終わりではなく、(答えを覚えていてもよいので)もう一度自分1人の力(自力)で答えに至るまでの考え方を説明(途中式も含めて)できるようになるまで繰り返すことが大切です。
数学は毎日の勉強の中で1度自力でできるようにしておけば、テスト前に特に勉強しなくてもテストでは点数が取れるので(水泳や自転車に乗るのと同じ)、普段の勉強の中で、自力でできるところまで仕上げておきましょう。
ちなみにテスト前は他の科目の勉強で時間をとられてしまうので、数学の勉強をテスト直前にやる前提で計画を立てると他の科目が終わりません。

数学はテスト直前には勉強しないという前提で毎日の勉強で自力で問題を解けるレベルまで仕上げておきましょう。
なお、数学は中高一貫校の場合、代数、幾何に分かれていることが多く、勉強法も多少異なるので、具体的な勉強法は下記を参照してください。
中学生定期テスト対策と勉強法~国語
国語については、できるかぎり授業中に勉強するつもりで疑問点などは解消し、テスト直前期は漢字の確認、教科書対応問題集のテスト範囲の問題を解く程度にしておくのが望ましいです。
実際には理科、社会でテスト前はいっぱいいっぱいになるでしょうから、国語はテスト前は漢字以外はやらないという状態になってもやむを得ません。

国語については、できれば学校の授業の中で勉強終了(後でやろうと思わない)というつもりで授業を受けるのが理想です。
国語も現代文、古典、漢字と勉強する科目が意外と多いので、それぞれについて具体的な勉強方法などは下記を参考にしてください。
中学生定期テスト対策と勉強法~理科
理科は毎回テスト1週間前に泣きながら勉強する科目かもしれません。それでも何とかなります。

「普段から勉強しておけばよかった」「次からは早めにやろう!」とテスト直前に毎回思うんだよな・・・。

理科(特に1分野)は、わからないときはさっぱりわからず時間だけが過ぎていくためテスト前は余計に焦るという科目なので、できれば、早めにやっておきましょう。
週末にその週の復習をするとテスト前がかなり楽になりますよ。
理科も1分野、2分野とあり、1分野は数学、2分野は社会に近いため、具体的な勉強方法は分野ごとに異なります。
理科が苦手な方は、下記も参照しつつ、早めの対策をするようにしましょう。
中学生定期テスト対策と勉強法~社会
社会は、テスト範囲を覚えきれるか、覚えきれずに力尽きるかで点数が大きく変わります。

中高一貫校の生徒さんであれば、テスト前日に睡眠時間を削ってでも社会は仕上げてきます(覚えてきます)ので、範囲が広くても意外と平均点は高い科目です。
社会は学年によって、地理、歴史、公民とあります。
どれも最終的には覚えれば何とかなる科目ではあります。最後まであきらめず頑張りましょう。
具体的な勉強法は下記を参照してください。
中学生定期テスト対策と勉強法~副教科
副教科も科目としては主要5科目と同じく、内部進学では評価されますので、しっかり学習しておくようにしましょう。
学校によっては、聖書などもあると思いますので、学校のテスト範囲をよく見て、前日にプリントだけでも見るようにしましょう。
副教科は、大学受験にはない科目なので、場合によっては、留年しない程度の勉強で十分です。
大学まである中高一貫校なのか、なくても指定校推薦を狙うのかなどによっても違うと思いますので、メリハリをつけながら勉強してください。
最後に
学年が上がってくれば内容も難しくはなりますが、試験の傾向もつかめるので、テスト対策はしやすくなると思います。
必要なら塾や家庭教師を活用するのも1つの手です。学校のプリントなどが整理されていれば、多少は何とかしてくれます。
ただ、最終的には生徒さん自身がやらないといけないので、普段から勉強する習慣をつけてもらうことが重要です。
中高一貫校は中学受験を突破した生徒さんの中で点数をとっていかないといけないので、ある意味中学受験より大変です。最初はお子さんと二人三脚でテスト対策に取り組んでいきましょう。